餌に飼育に血統に。
こだわりが光る京の地鶏。
「京地どり」

魅力は、深い旨みと心地よい噛みごたえ
地域によって食文化に違いがあるように、場所によって呼び名が異なる食材がある。すぐに思い当たるのが、主に関西で使われる鶏肉の別名「かしわ」だろう。一説によると、もともとは日本在来種の鶏のみを指す言葉だったとか。
そこで今回は、私たち関西人に馴染みの深い、本当の「かしわ」を求めて、「京地どり」を育てる外田さんの養鶏場を訪れた。
お話によると、美山地方で初めて京地どりの養鶏に取り組んだ、いわば第一人者だとか。そのきっかけから伺った。
「ブロイラーは低コストで幅広い料理に利用できるため、現在主流になっています。一方で平成元年くらいから、改めて昔ながらのおいしい鶏肉が欲しいという需要が日本全国で出てきました。特に京都は鶏肉の食文化が根付いていたこともあり、京地どりの可能性に着目したのです」。
農水省によると、地鶏肉は「在来種由来血液百分率が50%以上のもの」と規定されているが、京地どりは肉質の評価が高いシャモと黄斑プリマスロックを掛け合わせた「在来種100%」。まさに「かしわ」だ。
では、気になる味の特徴とは?
焼き鳥など、そのまま味わう調理法が一番と即答してくれた。特に鍋が適しているという。
「京地どりは長く煮込んでも固くならず、旨味もしっかりしています。何より、一緒に煮込んだ野菜までおいしくしてくれるのが魅力です。ブロイラーは味付けをして楽しむもの。京地どりは、肉自体の旨味を楽しむ食材だと思います」。
素材そのものが良いため、過剰な味付けはむしろ蛇足になるのかもしれない。ちなみに地鶏と名乗れるのは現在わずか約60種類。ブランド名を冠していても、多くは「銘柄鶏」と呼ばれ一線を画する。それほどに希少な滋味なのだ。
最近の夏は、鶏も熱中症に注意が必要
美山は雪の多いエリアだが養鶏に影響はないのだろうか?聞いてみると、近年は今までになかった悩みがあるという。想像を絶する夏の過酷な環境だ。以前は暑さで鶏が死ぬことなどなかったが、冷涼な美山であっても熱中症で命を失うことがあるそうだ。
「昔は寒さに苦労しましたけど、今は夏の方が大変ですね」。
その言葉通り、暑さ対策はひと工夫も、ふた工夫も手を打つ。飲み水に氷を入れるほか、暑さを乗り越える体力をつけるため、特別な栄養成分を添加するなど餌の配合まで変える。また、鶏舎に扇風機を回したり、スプリンクラーで屋根の上から水を出したり、鶏が快適に過ごせる努力を欠かさない。
特別なおいしさのために、手間と時間を注ぎ込む
飼育でこだわるのは長い飼育日数だ。基準に従えば地鶏は75日で出荷できる。ところが外田さんは90日まで育てるという。理由は、当然「味」のため。身体が大きく育っても、旨味が乗るにはもう少し時間がかかるとか。効率だけを考えるなら、早く商品にしたいのが本音だろう。長く置くほど餌代もかさむ。しかし、質を落として顧客の支持を失えば本末転倒だ。
「基準ぴったりで出すこともできますが、そこは譲れないところです」。
飼料も手間と技術を注ぎ込んだオリジナルブレンドを貫く。
「手作りすることで成長に合わせた餌ができます。自家製飼料用米や籾米、竹粉も特徴です」。
なぜ竹粉や籾を?栄養もなさそうだが…?引き続き教えてもらった。
「鶏は歯がない代わりに、筋肉の塊でできた胃『筋胃(きんい)』を持ち、食物をすりつぶして消化します。竹粉と籾に養分はなく吸収もできませんが、硬い繊維質は筋胃を活発に動かす効果があり消化吸収を促進するのです」。
健全な成長は、健康な胃があってこそ。美味の秘訣は枚挙にいとまがないほどだ。
嬉しい日や記念日に、京地どりという選択を!
まだ「京地どり」は認知が低いという外田さん。ちょっといい日に選んでもらえるような存在になって欲しいと望む。いずれは京野菜などに並ぶ存在感をめざす。
[取材日:2025年2月4日]

寒さから雛を守るために、こたつを利用した自家製の暖房器具も活用する。専用の装置も販売されてるのだが、手作りするのが外田さん流。


徹底した鳥インフルエンザ対策を実施。防鳥ネットの設置はもちろん、鶏舎の周囲は消毒用の石灰を敷き詰め、鶏舎ごとに長靴を分ける。

飼育は、伸び伸びと過ごせるよう、平飼いにし、あまり密にならないよう気を配る。窮屈だとストレスによって成長が悪くなるだけでなく、冬季は温もりを求めて鶏が寄り集まり、下敷きになることもあるからだ。

販売は、基本的に京都の飲食店などへの直接販売がメイン。小売りは美山近隣の道の駅や、観光名所「かやぶきの里」などに冷凍のパックを卸す。一つのパックに、ホルモンから腿、胸など多彩な部位が入っているのが特徴だ。また、直接電話で注文すれば捌いたばかりのフレッシュな素材も購入できる。
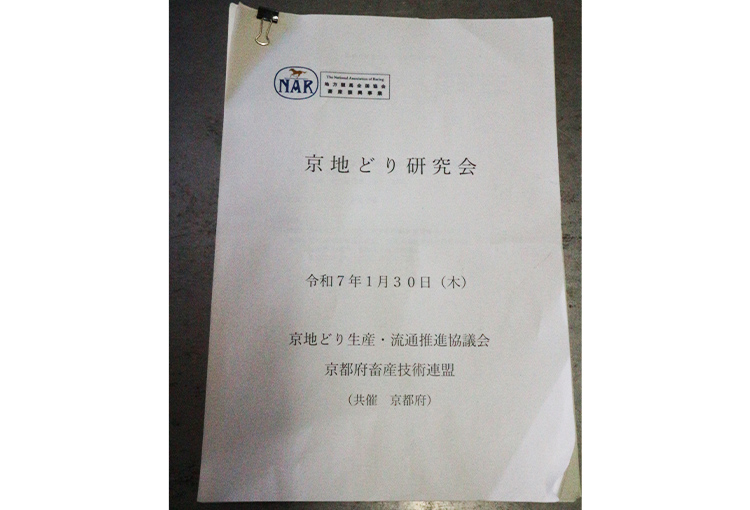
新規養鶏者をサポートするため、定期的に研究会を開催。講師を担当するほか、見学も受け付ける。「大切な伝統は受け継ぎつつ、時代に合わせて革新しながら、次に繋げてもらいたいですね。そういう若い人たちが現れてくることに期待しています」。

元々初代が採卵鶏の養鶏を始めたのが外田養鶏場のルーツ。今も採卵鶏として「モミジ」という品種を育てる。こちらも、味と品質で人気を集めている。
餌に飼育に血統に。こだわりが光る京の地鶏。「京地どり」
- 取材協力
- 外田養鶏場
- 京都府南丹市美山町内久保池ノ谷1-1
- 事業内容:美山の地玉、京地どりの生産および販売。
[ 掲載日:2025年3月21日 ]


