関西の食に思う
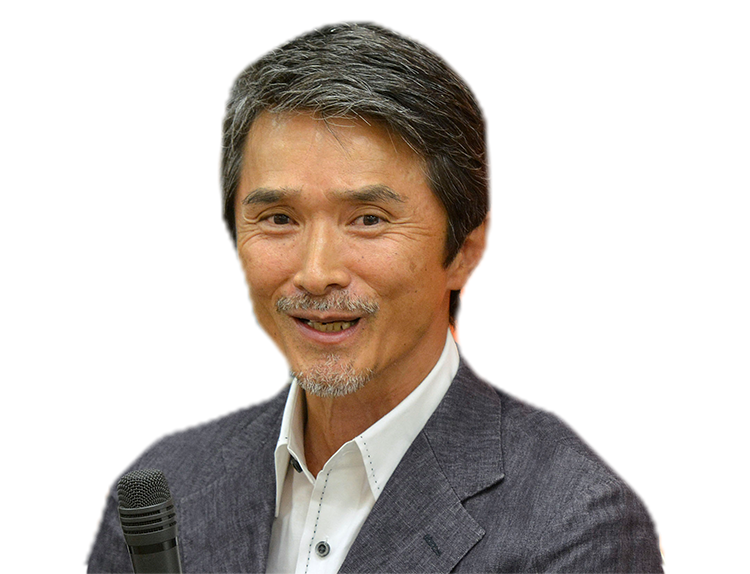
関西の中国料理が元気だ、との話を東京や横浜の知人たちから聞き、それらしき店を数えてみる――。確かに30席に満たないカウンターから厨房が見える形式の店が増えています。この手の店は昔から地域密着型で独立開業のビジネスモデルでもあります。ここまでは同じですが、話題にあがる店のメニューにはエビチリやチンジァオロースーはなく、頼めば出てくるのでしょうが店に来るお客も心得ていてナマコの発酵唐辛子炒め、スッポンの香草蒸し、フカヒレと黄ニラの炒め等々、壁に向かって鍋をふり続ける30、40代のシェフの所作とこだわりの料理を楽しんでいます。
 シェフに共通することはSNS世代で情報の収集・分析と応用力に長け、時間を惜しまず研鑽に励む。視線の先には中国があり、大陸各地に足を運び、その地の食文化に触れ見聞を広めることを怠らない。大陸は彼らには一衣帯水、料理はまず足で食べるものなのです。
シェフに共通することはSNS世代で情報の収集・分析と応用力に長け、時間を惜しまず研鑽に励む。視線の先には中国があり、大陸各地に足を運び、その地の食文化に触れ見聞を広めることを怠らない。大陸は彼らには一衣帯水、料理はまず足で食べるものなのです。
関西、関東は何かにつけて比較され外食産業も東高西低と言われますが、それも東京VS京都・大阪・神戸、三都で東京に立ち向かうのでは悩ましい限りです。
関西の食文化とその歴史は誰もが認めるところで、京都や大阪には奢侈な文化があり料理人、お客にも贅沢という名の余裕を持つことを強く求めてきました。暖簾の仕立て、打ち水の作法ひとつにも厳しさが見えます。料理人と贔屓さんの矜持が料理の背後を支えてきたと思っています。
かつてはこの歴史観が関西の外食産業に新しいビジネス、食文化の芽生えを生むことを抑圧しているのではないかと考えたことがありましたが、今やその心配はなく、あんずるのは奢侈な文化の復活です。
美術におけるイギリスの知性は「今、我々に欠けているのは芸術家ではない。大衆である。芸術に意識を持つ大衆ではない。無意識的に芸術的な大衆である」といっています。我々の業界においても然りで、若いシェフの登場・活躍は不可欠ですが、キーワードは無意識的に料理人的な大衆なのです。こうした大衆の果たす役割は大きく、その数と層の厚さがすなわち食文化の豊かさを裏づけていると思われますが、東京に行くたびに遠く及ばないと痛感させられます。
ジャンルは問わず、いつの時代も真っ白なコックコート、よどみのない所作、料理人の後姿は魅力的です。若手シェフの数も増え、活躍する姿を目にする機会も多く、業界人として嬉しい限りです。
関西食文化研究会、会員の皆様の行動自体が、業界人だけではなく料理人的な大衆を増やしていく啓蒙であり一助になると考えます。更なるご協力と積極的な参加をお願いしたいと思います。
[掲載日:2017年7月3日]
吉岡 勝美氏の今注目する料理人
河田吉功氏は国内、台湾で研鑽を重ね、1986年に代官山のビルの地下に20坪ほどの「RINK」をオープンした。屋号はチベット語で蓮の花を意味する。名刺には「料理には旨味調味料、砂糖は使用していません」と書いてあるくらいだから、かなりこだわりの店である。その後に渋谷に「文琳」をオープン。いずれの店もオープン・キッチンである。それまでにもこの手の店はたくさんあったがシェフがお客に背を向けて鍋をふる店は新鮮だった。お客はカウンターでシェフの後姿、所作を見ながら料理を楽しむ。作る側はやりにくいと思う。客の視線を背中に浴びるのであるから。河田氏は食材とシンプルな調味料の組み合わせから多彩なおいしさを作り出すといわれ、そのオリジナル性の高い料理は多くの中国料理ファンを魅了してきた。近年中国料理業界ではカウンター形式のハイカジュアルな店が注目されている。シェフたちは今も壁に向かってこだわりの料理を作り続けるが河田吉功氏は先駆者的な存在である。六本木「新葡苑 龍滕」の取締役総料理長として活躍。2016年12月末に閉店した。現在、河田氏は新店のオープンに向けて充電期間中であるが多くの人が再登場の時を楽しみにしている。


