年齢と技術の習得
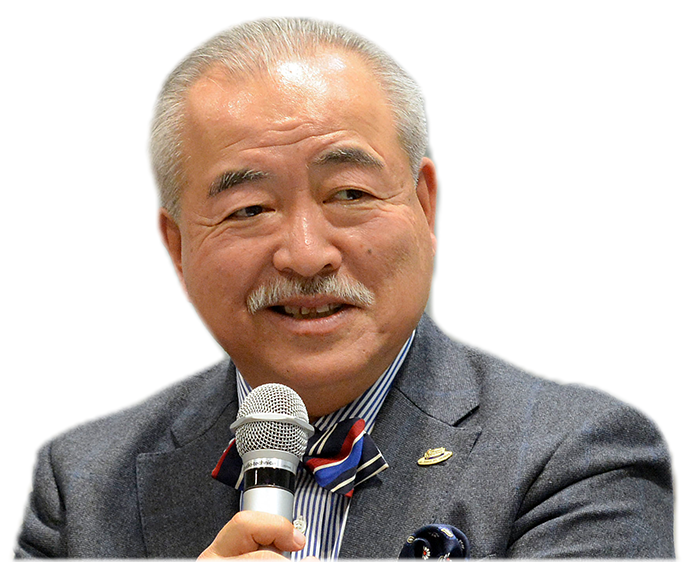
毎月各地を旅する生活が何年も続いている。
そこでいろいろな人物や生産物と出会い、刺激や元気をもらう。
コーヒー好きの僕は、どの街でもコーヒー店に訪れる。行き先が決まるとその地名と自家焙煎というキーワードを打ち込む。すると数軒クセのありそうなコーヒー店が見つかる。じつはこの存在が、重要な情報源になることがしばしばある。コーヒーを淹れるのに、他人が焙煎した豆では納得がいかず自ら焙煎する人物は食に関しても一家言あるにちがいない。そのマスターから仕入れる情報は信用たるものが多い。そしてマスターと懇意になり、いまだに情報交換をし続ける人物が各地に点在するようになったのだ。
 群馬県桐生市でとてつもない焙煎技術の持ち主に出会った。
群馬県桐生市でとてつもない焙煎技術の持ち主に出会った。
店名は「ホライズンラボ」でコーヒーの豆の販売のみ、かつ営業形態が月初の7日間だけというのだ。焙煎士は岩野響さん、御年15歳である。高校に進学せずコーヒーの世界に飛び込んだ。彼が小さなパフレットに記した言葉に「読書、写真、版画、料理、盆栽・・多様な趣味の傍らにいつも飲んでいるコーヒー。ふとそのコーヒーに注目してみると淹れ方や豆の種類、焙煎の仕方など奥深い世界がそこに広がっていました。コーヒーの表現は大海のように広く、絡まっていた自分の心が解き放たれるのを感じました。(中略)ホライズンラボは、ぼくができることを探し出し、様々な人と関わりを学び、最終的にはぼくしかできないことを見つけるための研究室です」とある。
その豆を購入し、飲んでみた。驚きである。焙煎技術の高さもさることながら、彼が目指している世界が明確に伝わるのだ。完成形をきちんと理解し、そのために何が必要で、何が不要なのかが分かっている味わいであった。
この豆を飲んだ、コーヒー店のオーナーは「すごいですね。これが15歳の人が焙煎したとは思いません」と述懐した。この豆を飲むと技術とは一体なのだろうと思ってしまう。最近14歳・15歳の活躍が目立つ。スポーツの世界では10万時間レッスンすればプロとして必要な技術は身に付くといわれている。スタートが4・5歳であればそれは十分可能なことである。しかし、料理の世界は少し事情が異なるが、この15歳の焙煎士の仕事振りをみると、いかに自分が目指す世界観を構築するかが重要だと思う。そのためには多種多彩な情報の入手と人物との交流が不可欠となる。
そのために関西食文化研究会は存在する。それをどのように活かすかは会員の意識にかかっているのだ。投げるべき球を持っているのは会員である。その球をどう活用するかをもっと考えてほしいのである。
[掲載日:2017年8月1日]
門上 武司氏の今注目する料理人
ここ数年間でもっとも感銘をうけた料理人は、静岡の「成生」という「板前てんぷら」の志村剛生さん。
昨年の夏に初めて訪れて以来、毎月この「成生」の天ぷらを食べるだけに静岡に通っている。天ぷらといえば東京(江戸)が本場であるとこれまで信じていた。たしかにそのカテゴリーの最高峰は東京にある。
また、和食の世界において「天ぷら」と「うなぎ」は非常に変化しにくい料理でもあった。その料理をいかに新しく捉えることができるのか。それを具現化したのが「成生」となる。
天ぷらは素材に粉とコロモをつけ、油で揚げる料理だ。それも油の中では、そんなに長時間入れて置くのではなく、さっと揚げる。また揚げたてをすぐの食べるのが定石であり、海老は天ぷらを象徴する食材でもある。
この観点をことごとく覆してくれるのが「成生」だ。これまで7回訪れたが、海老が供されたのは2度だけ。
「浜名湖の天然のいいのが入らないと揚げません」と。しかし、海老が入ったときの印象は、海老がなくても全く問題なし、主役と感じることはなかった。
1本のアスパラガスは2つに切られ、揚げる時間によって食感も味わいも香りも全く別物になる。これだけでも衝撃であった。根菜類はおよそ40分油の中におり、揚げてからも10分程度は寝かせる。つまり予熱で火を入れることになる。
天ぷらという料理が、揚げるだけでなく、蒸し、焼く、予熱などを合体化した料理であることを認識させてくれてあまりある一軒だ。魚介類も食材によって調理は自在に変化するのだ。
油を使った新しい料理との出会いともいえる。


