人材
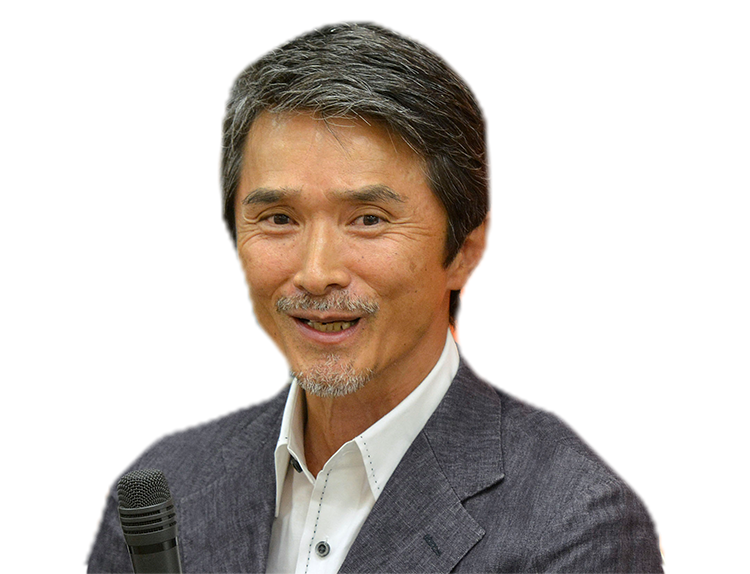
世界で類を見ない速さで少子化・高齢化が進行しており、生産年齢人口は今後減少していくことが確実となっている。政府(文部科学省)は持続的な発展、成長のために、数年前より大学設置基準の改正や専門学校の新しい教育制度の認定、新たな教育機関の創設などの検討を進めてきたことは周知である。
大学では、平成23年に大学、短期大学設置基準が改正され、社会的、職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制整備を図ることが義務付けられた。また平成27年には、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」として文部科学大臣が認定する制度が創設されている。
専門学校では、平成25年に、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専門課程を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定する制度が創設され、平成26年よりスタートした。就業年限2年以上で、企業や団体と連携して授業科目開設・教育課程編成、実習・実技の授業などを実施する。この「職業実践専門課程」は「教育訓練給付金」の対象講座となる。加えて在職期間中に給付される「教育訓練支援給付金」の両方が支給されることで社会人がこの課程がある専門学へ再入学しやすくなった。転職する際の学び直しに門戸を開いた制度となっている。
文部科学省は新たな教育機関として「専門職大学」の創設を決定し、31年よりスタートする。1~2年制、3~4年制があり、企業との共同教育計画の策定、企業等における指導員の配置など、適切な指導体制が確保された企業内実習等について、一定時間以上の履修を義務付けると共にこれを含めた実習等の科目または演習及び実習等の科目全体の割合についても一定割合以上を義務付けるとある。この専門職大学は大学体系に位置付けられ、高等教育機関(大学、短大、高等専門学校、専門学校など)からの編入、あるいは卒業し就職等をした社会人が学び直しのために編入学することも可能とある。
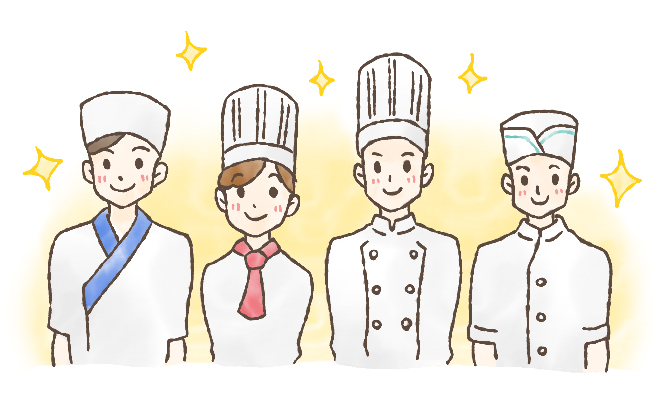 入職前の若者や現職の職業人をはじめ働く人々の様々なライフステージに応じて、教育の機会が提供される、学び続けるための環境整備が進んでいる。従来、日本の企業は大学等で何を学んだかは余り重視しない傾向が強く、専門的な技能、知識の育成は社内教育でと考える風潮がある。また技能教育に強みを持つ専門学校は入職前の若者の進路の受け皿として大きな役割を果たしてきたが、その一方で質保証・向上の面で課題があるとの声もある。産学連携をこれまで以上に推進することで、卒業時の質の保証、社会で即戦力となる人材養成を促す、また企業内に集積された情報を理論化・体系化して、生産向上へとつなげることも期待できる。特に専門職大学には企業等における事業、実務の主力を担うと共に、新たな価値観の創造を先導する役割を担うことができる人材の輩出が期待される。
入職前の若者や現職の職業人をはじめ働く人々の様々なライフステージに応じて、教育の機会が提供される、学び続けるための環境整備が進んでいる。従来、日本の企業は大学等で何を学んだかは余り重視しない傾向が強く、専門的な技能、知識の育成は社内教育でと考える風潮がある。また技能教育に強みを持つ専門学校は入職前の若者の進路の受け皿として大きな役割を果たしてきたが、その一方で質保証・向上の面で課題があるとの声もある。産学連携をこれまで以上に推進することで、卒業時の質の保証、社会で即戦力となる人材養成を促す、また企業内に集積された情報を理論化・体系化して、生産向上へとつなげることも期待できる。特に専門職大学には企業等における事業、実務の主力を担うと共に、新たな価値観の創造を先導する役割を担うことができる人材の輩出が期待される。
外食・中食産業は個人の関心やライフスタイルが多様化していく中で、多彩なサービスを提供することで折り合いをつけてきた。専門人材の豊かな創造力・実践力を最大限に引き出し活用することが求められる時代でもある。次世代型産業を担う人材育成へより一層尽力したい。
[掲載日:2018年1月9日]
門上 武司氏が何度も読みたい本
本を読むことは、著者の知識・見識・経験・哲学などを学ぶことです。
また本はつぎつぎと新たなヒントをもたらしてくれます。つまり本は本を呼び、どんどん自身の知識欲を拡大する装置として最適だと考えます。 本を読むことで、自らの姿勢を見直すことにもなるのです。
というのは、優れた著作は、著者がそれまで考察した膨大な蓄積の一部を表したものです。よって、それを読み込むことで、視界がひろがり、思索するトリガーが埋め込まれています。
今回、僕が選んだ三冊は『食』というテーマで、そこまで視野を広げることが可能となるのか、そんな提案も含めての選択です。
推薦書籍
- ①「食と建築土木」 後藤治・二村悟著 LIXIL出版
- 日本の原風景。農山漁村部では、建物や町並み以外に不思議な構造物が目に入る。それらは地方の食と密接に結びつくことが多い。大根を干す櫓、砂防、階段上山葵田を初め、建築土木の視点から推察する「食」は極めて興味ふかいのです。
- ②「飼い喰い 三匹の豚と私」 内澤旬子著 岩波書店
- 自分で育てて食べる。豚を育てることは想像以上に手間がかかり、その分愛着も湧いて くる。可愛がった豚を最終的には自ら食べることになる。直感的に可哀想と考えるのだが、それはあくまで人間の勝手な思い込みにすぎないのです。食べることの本質に迫る一冊です。
- ③「メニューは僕の誇りです」 斉須政雄著 新潮社
- 東京・三田の「コートドール」オーナーシェフ・斉須政雄さんの著作には、いつも心をあらわれるのです。料理人として料理をつくるミッションをここまで徹底的に突き詰めた稀有な例だと思います。料理を目指す人、味わう人に読んでいただきたい一冊です。
「株式会社ジオード」代表取締役 「あまから手帖」編集顧問
門上 武司氏


