料理人の守備範囲は広い!
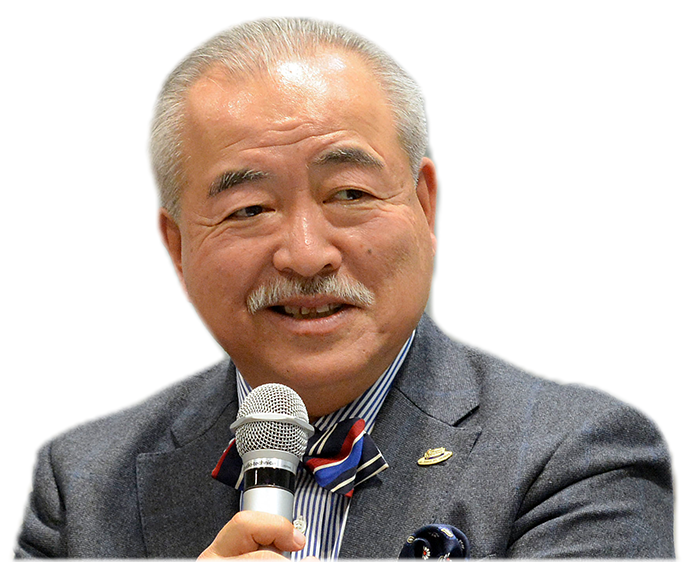
レストランに入った時に、70歳を超える元フランス料理のシェフは眉を曇らせた。その原因はレストラン内に流れる音楽だと思った。案の定、レストランの料理人に「音楽、もう少しボリューム落としてくれる」と言葉をつないだ。元シェフはいつも「レストランのオーナーシェフは経営者出なければならない。そのためには料理だけでなく、その場の雰囲気などにも目配せしなければならない」と話す。
飲食店におけるBGMは大きな課題だと思う。前述のレストランでは明らかに料理人の好みが反映されていたのだろう。あまりにも個性的なロックミュージックが流れていたのであった。フランス料理店だから何もシャンソンやフレンチポップを流せと言っているのではない。日本料理店で琴の調べが流れているとこれもまた興ざめである。簡単なのはUSENから無難なチャンネルを選ぶことだ。またはシェフもしくは音楽好きのスタッフが好みのCDや編集した音楽を流す場合も多い。
 しかし考えて見ると、レストランの設計、デザイン、カトラリーの選択などプロフェッショナルが関わることが多い。だが、音楽に関してはプロフェッショナルが関与したこと耳にしたことがない。音楽は人間の記憶や感情に左右する大きな要素である。これは今後、飲食店が考えなくてはならない事柄かもしれない。 先日、京都のコーヒー専門店のカウンターに座ると他の珈琲店とは全く異なる音楽が流れていた。「こういう店はジャズを流すところが多いのですが、インターネットラジオから好みの局を選んでいます」と答え「外国の方がすごく反応してくださいます」と加えた。
しかし考えて見ると、レストランの設計、デザイン、カトラリーの選択などプロフェッショナルが関わることが多い。だが、音楽に関してはプロフェッショナルが関与したこと耳にしたことがない。音楽は人間の記憶や感情に左右する大きな要素である。これは今後、飲食店が考えなくてはならない事柄かもしれない。 先日、京都のコーヒー専門店のカウンターに座ると他の珈琲店とは全く異なる音楽が流れていた。「こういう店はジャズを流すところが多いのですが、インターネットラジオから好みの局を選んでいます」と答え「外国の方がすごく反応してくださいます」と加えた。
飲食店の音楽を始め、オーナーシェフは料理の味わいは当然のことながらその場の雰囲気をどう演出するか、これも不可欠な要素である。
[掲載日:2018年2月1日]
山口 浩氏が何度も読みたい本
料理人に限らず自分では経験できなかったり、考えの及んでいなかったことなどを書籍から学ぶことの重要性は言うまでもありませんが、インターネットなどの普及により調べたいことなどピンポイントで検索できるようになる事で書籍に触れるきっかけそのものが減ってきていると思います。調べたい事があり書籍を手に取り思いがけず読み込んで行く時の時間経過は私にとって非日常の世界に入り込むようなワクワクした感覚です。また、書籍から学んだ事項が自分の中のロジック作りにも不可欠です。
推薦書籍
- ①フランス料理の源流を訪ねて(ロベール フルソン著)
- 異国の料理を学ぶ上で、その料理の出来上がったテロワールを感じることは、その料理の 根の部分を知ることだと思います。ここから派生させて花や実をつけることが肝要と思います。
- ②中央公論社の「シェフ・シリーズ」77号を持って終了
- 個性豊かな料理人たちが自分の学んできた過去の歴史にその料理人の個性とその時代を反映させた料理は多種多様で興味深く、これからの料理の進むべき進路を暗示していたシリーズではないでしょうか。
*上記は絶版。ネットで購入できるときもある - ③フランス料理 軽さのテクニック(山口 浩著)
- 1992年日本に上陸したベルナールロワゾーの手法は必ず日本のフランス料理の流れのひとつとなると信じて日本のフランス料理界に投じたメッセージの集大成。2018年日本のフランス料理の流れはどのようになったか。興味深いテーマです。
- ④フランス料理の「なぜ」に答える(エリヴェ ティス著)
- フランス料理の魅力のひとつは科学的エビデンスが確立されていることだと思います。その基本的知識を披露した本書はフランス料理の進化に大きな力を与えるでしょう。
- ⑤「こつ」の科学 調理の疑問に答える(杉田 浩一著)
- 見て、感じて学ぶから科学的に学ぶことの重要性は今や当然のことですね。本書は分かりやすく調理のサイエンス的学習法を手助けしてくれる貴重な書籍です。
「神戸北野ホテル」総支配人・総料理長
山口 浩氏


