飲食店のSNS活用法

僕の本業は、テレビ番組プロデューサー、ディレクター(2001年に立ち上げた『水野真紀の魔法のレストラン』や『真実の料理人』シリーズなどを制作)です。30年近い取材を通して、なぜその店が繁盛しているのか、なぜメディアに取り上げられるのか、インターネット上で話題なのかがわかるようになってきました。逆に流行っていない店も何百軒と見てきて、なぜ流行らないのかわかるようになりました。
食べ手としては、Facebookを中心に【麻婆十字団】【日本洋食遺産ドミグラス修道院】【塊!ステーキ団】【鮨狼】など20近い食べ歩きグループを主宰。堀江貴文氏がプロデュースする全国の食の達人が「旨い店だけをアップする」グルメアプリ「テリヤキ」の【テリヤキスト】に選ばれ、また食べログの【グルメ著名人】として、年間500店以上食べ歩いて情報を発信しています。
メディア関係者とSNS発信者という2つの立場から、これから開店する、あるいはもっと店を繁盛させたいと思っている人向けに、今回はSNS活用法にしぼって、ズバリ書きたいと思います。
僕のFacebook上の「友達」は4500人。そのうち飲食店関係者は、ざっと500人くらいでしょうか。タイムラインで日々、いろんな書き込みに触れています。上手に利用されている店は、確実に集客につながっていますが、そうでない残念なケースも多々あります。
SNSは、自分の店、料理、そして自分自身のファンを増やしていくためのツールとして戦略的に利用すべきだと僕は思います。
まずは、
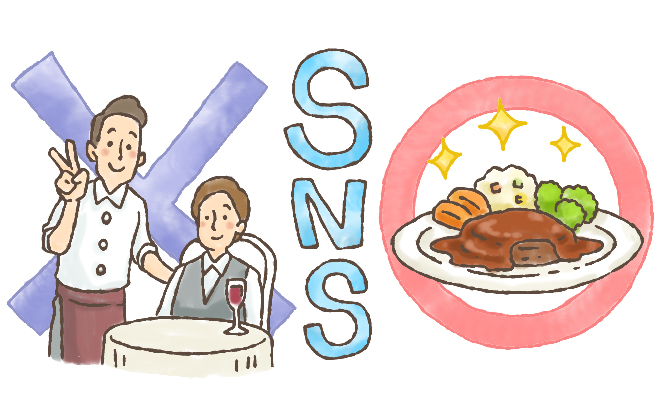 【SNSに書いてはいけない。やったら損なこと】
【SNSに書いてはいけない。やったら損なこと】
●客の悪口。他店の悪口。売り上げが上がらない、というようなネガティブなこと。
要は、SNSでストレスを発散しないこと。何人かの人は共感、同情の書き込みをしてくれたり、慰めてくれたりするでしょうが、その他の人たちは、確実に印象を悪くしています。少なくとも僕は、「今日来てくれた客、何もわかっていない」「チャラチャラした料理を出している店が流行っているのが許せない」というようなことを書くシェフの店には行きません。メディアも取材したくはならないでしょう。ネガティブな発言をSNSでする人は、ネガティブなオーラをまとっていて、店に行ってもそれを感じるからです。楽しくない。
●頻繁に自撮り写真を載せる。
アイドルならまだしも、自分好きすぎ?なぜそのシチュエーションで自分が映る必要があるの?とどん引きします。(もちろん嫌みに映らない人もいますが)。また、きょうはこんなお客さんが来てくれました。とVサインをしてお客さんと一緒の写真をバンバン載せるのもマイナス効果です。格が下がり、小さな人間に思われます。訪問者が有名人の場合もしかり。有名人は写真を載せて良いと許可を出しても、自分が宣伝に利用された感を持ちます。再訪問を無意識レベルでも避けるでしょう。
では、
【SNSに何を書くべきか?何を載せるべきか?】
●おいしそうな料理写真
照明の当たり具合を考えて撮ったとびきりおいしそうな料理写真とその料理の簡単な解説。
撮影はスマートフォンでも十分です。これをFacebook、Twitter、Instagramで、毎日アップする。「毎日」ということころがミソで、接触する機会が多くなると好意の獲得につながる単純接触効果(ザイアンスの法則)を狙うのです。朝ドラのヒロインも毎日見ている内に、好感を持つようになるのと同じです。メデイア関係者の目にとまる可能性が上がり、取材依頼がくる可能性も上がります。たとえば、ウニとトマトの冷製パスタのおいしそうな写真に、「ミョウバンを使っていない生雲丹仕入れました。今日から3日間、1日限定10食です」と書かれたら、うわあ行きたい!と思う人が何人もでること必至です。翌日は、写真を変えて、「この〇〇さんが作ったトマトはきんきんに冷やしています。あと2日間1日限定10食です」と書きます。逆に、おいしそうでない食材の写真はNGです。解体したジビエの写真とか一般人は見たくありません。
●読み手が知識を得たり得をしたりすること
たとえば、毎日市場に行くシェフなら、良い鯖の見分け方とか、マグロはどこを見るとか、今年初めて松茸が出ましたとかを書きます。料理人なら誰でも知っていることで良いのです。あるいは新しく作ったドレッシングのレシピや、新作麻婆豆腐のポイントなど…。読み手が何かしら得をする、自分の知識やテクニック、情報を思い切って公開してしまいます。「へえ、面白い」と読者が少しでも思うと、また読みたくなります。読者の関心を継続的に得ることができるのです。同業者に真似されるのが嫌でしょうか? タダで書くなんて損でしょうか?今の時代にそんな狭量な考えでは生き残っていけないと僕は思います。
結論です。
自分の店だけが流行れば良いという視点ではなく、つまるところ、おいしそうな料理写真の公開も含めて、「食文化の発展に貢献する」視点で書くと、本来の意味で因果応報、イメージアップにつながり、必ずファンが増えていきます。
[掲載日:2018年8月1日]


