「レストランがなくなる日」は本当に来るのか?

「レストランがなくなる日」。2010年の暮れに主婦の友社から出した私の新書のタイトルだ。「なくなる日」シリーズのひとつで、他に「ドル」「ラーメン」「暮らし力」「政治家」など、なくなると困るものをテーマに専門家が現状と問題点、解決策を考えるという内容だ。その書き出しは、当時、世界で話題になっていたデンマークのレストラン「ノーマ」についてだった。世界のベストレストラン50でNo.1になったばかりの若きシェフ、レネ・レゼッピ氏は「どんな場所であろうとも世界一になることは可能だ!」というメッセージを発信して世界中の若い料理人に夢と希望を与えた。彼を目標に、世界を目指す若い料理人たちが急増するきっかけになった。
その当時から料理業界にとってもっとも大きな問題は、人手不足だった。シェフはいるが、シェフを支える若手が育たない。軍隊のように厳しい長時間労働、トップダウンの命令系統で成り立つ古い体制のレストランは、若者がもっとも嫌う職場だ。「ノーマ」が新しい体制のお手本になったのは厨房スタッフ、フロアサービスとも全員参加の「チーム」というコンセプトだった。問題があれば全員が理解するまで話し合う。そこから一丸となったサービスが生まれる。料理を作った厨房のスタッフも客席に出て料理の説明をする。レストランは新しい時代に移行し、古い体制のままでは自然淘汰されるだろうと予測された。
あれから8年、人手不足はさらに深刻な問題になっている。東京では「もう、人を探すのはあきらめました」と規模を縮小する店も多い。しかし30代、40代のオーナーシェフたちはその危機的状況を少しでも打破しようと様々な手を打っている。銀座や六本木など中心部に店を構えるのではなく、代々木上原、学芸大学、武蔵小山など私鉄沿線に小規模な店を構える。カウンター席を基本に客との距離を近くする。地元客の支持を得ると、すかさず隣り駅や、同じ駅でも違うコンセプトの2店目、3店目を出す。ここでポイントになるのがスタッフの集め方。常連に声をかける。この店が好きで通ってくるのだから、店の良さもお客ののぞむところもよくわかる。いちばん強い味方だ。
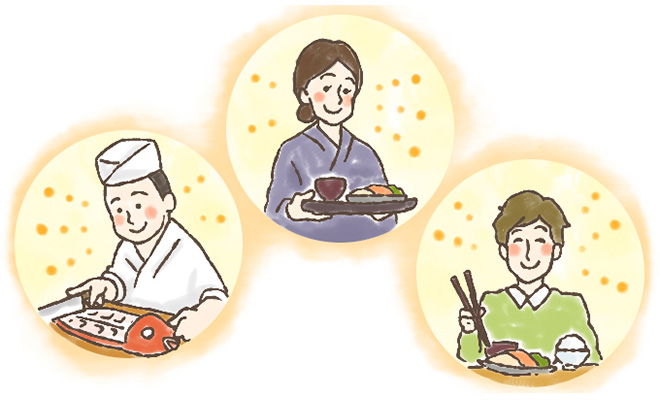 「僕は決して自分だけ儲けたいわけじゃない。少しでも長く、楽しく働きたい。レストランが好きだから、お客さんにも楽しんでほしい。そして一緒に働いてくれる仲間たちも、みんな幸せになって欲しい」「人間らしい生活ができなきゃ長続きしません。安いだけで人を呼んでも、長続きしません。やっている僕らが楽しくなくちゃ、おいしい料理なんて作れない」。きちんと休みをとる、勉強会として地方のレストランに行く、1年に1回はご褒美に海外旅行に行く。決して甘やかしているのではなく、そこで同じ体験を共有することが仕事につながる。シェフのもっとも重要な仕事は、スタッフ一人ひとりが自分の働いている店を誇りに思える場所にすることだ。それは世界一でもない、星付きでもない。いつまでもそこにある店。学び続けるレストランは、決してなくならない。
「僕は決して自分だけ儲けたいわけじゃない。少しでも長く、楽しく働きたい。レストランが好きだから、お客さんにも楽しんでほしい。そして一緒に働いてくれる仲間たちも、みんな幸せになって欲しい」「人間らしい生活ができなきゃ長続きしません。安いだけで人を呼んでも、長続きしません。やっている僕らが楽しくなくちゃ、おいしい料理なんて作れない」。きちんと休みをとる、勉強会として地方のレストランに行く、1年に1回はご褒美に海外旅行に行く。決して甘やかしているのではなく、そこで同じ体験を共有することが仕事につながる。シェフのもっとも重要な仕事は、スタッフ一人ひとりが自分の働いている店を誇りに思える場所にすることだ。それは世界一でもない、星付きでもない。いつまでもそこにある店。学び続けるレストランは、決してなくならない。
東京を中心に地方や海外の食文化、レストラン事情を最前線で取材。ファッション誌から専門誌まで数多くの雑誌・WEBで連載を持ち、その店の良さ、時代性をわかりやすく解説。農林水産省顕彰制度・料理マスターズ認定委員。「世界のベストレストラン50」の日本地区の投票者代表を2007年より7年務める。
[掲載日:2018年10月1日]


