無限に拡張する懐石料理

日本料理を代表する懐石料理は、コースの流れの緩急を表現することに大きな特徴がある。油脂の美味しさに依存せず、飽きない美味しさを長時間継続することが可能である。これは日本という世界にも類稀なる風土において独立した食文化を長き時代に渡って培ってきたことに起因する。日本の気象条件と地理的要因から生じる300種類を超える魚介類の多様性と品質の良さ、土壌の肥沃さから高品質の米や多種多様な野菜の栽培、それらの食材をうまく編集する昆布と鰹節の存在、これらの特殊な食のトライアングル構造は互いを意識し、互いを調理技術や栽培技術の高度化によって品質を向上させてきた。
そして、先人達は単に美味しいだけに飽き足らず、如何に気分を高揚させるか若しくは安息して食事が出来るかといった心の情動に関与するための工夫にかなりの労力を費やし、食べることに栄養以外の意味を付加してきた。それは情報による美味しさであり、既存の日本文化を知れば知るほど料理の美味しさが深く感じられるように緻密に仕立てられている。
懐石料理は日本の伝統芸能である茶道・華道・能楽と全く同様の構造を持ち、型として一部を取り込んでいる。お抹茶を飲んで清々、花を生けて可憐、仕舞を見て優雅、実際はそれだけではなく水を打った露地を通って静謐な茶室に入り翳りある僅かな光と音を頼りに阿吽の呼吸の中、さらさらと茶を点てる。その時に脳内に巡らせる心の動き自体が一碗飲む美味しさに直結している。イメージが広がった世界から一碗に存在する深緑の一円に一気に全身の知覚が集中するのである。自分と仏様の間にお供えした供花はそれ自体を結界として相容れないものでありながら、自分の意識を伝え無言の対話をするために存在している。同じ花を通してそこに安穏という概念が生まれるのである。能の仕舞に於いても扇の所作として右手に持った閉じた扇を上から下に降ろすだけであるのにその間と降ろす速度の微妙な加減によって清水寺の音羽の滝を表現したり、観客の眼に那智の滝に映ったりするのである。これらの人の情動に作用し主たる目的に完結させる手法は同様に料理そのものにも反映されていると考えられる。
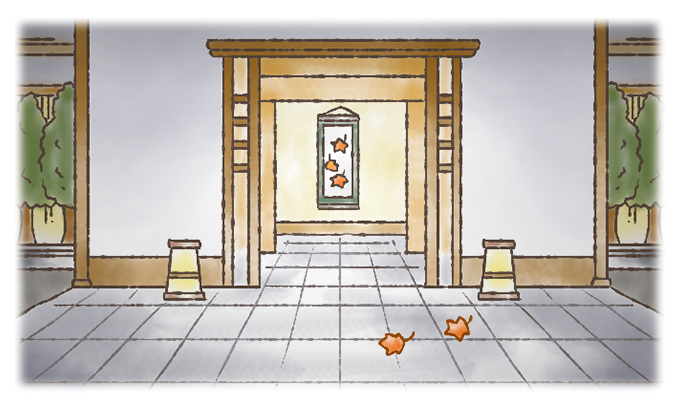 茶道は茶と碗、華道は花と花器、能楽は謡と仕舞、料理は食材と器の関係がミニマムな世界であるが、料亭の懐石料理となると、料理を食することが主たる目的ではあるがこれら様々な伝統芸能からくる断片的な手法は同時且つ付随的に表現されることになる。料亭の明かりに導かれ長暖簾をくぐり、水を打った少し勾配のある露地を通る。日常から別離し非日常感を演出する。玄関には季節の軸が掛かり、その日のもてなしのテーマが映し出される。そしてその季節に関連した魚介類と野菜が調理され料理として供される。香が焚き染められ僅かに感じられるか感じられない程度の柔らかな香りに気分が落ち着く。料亭は個室なので、部屋ごとの設えはそのお客様の目的に応じて仕立てられている。お祝いの際には、能楽にもある「高砂」:世阿弥作(住吉明神の化身の老人夫婦)のお軸などをかけ、松をあしらった八寸を供し、長寿繁栄を願う気持ちを表現し、語ることなく相手に伝えるのである。基本的には「高砂」は春の演目であるので花入れには雪と春を印象付ける白梅を生けることになる。お席に着き、辺りを見回すとやや遠くに庭が見え、ガラス窓を挟んで縁側があり、その内に障子がはめ込まれ、上座には入り組んだ床の間があり、一番近いところに相伴する方々の顔がある。この凸凹した距離感の違いは狭い空間でも目が疲れず飽きない空間になっていて、されど強く目を引くものは全く存在しない。その状況下において食前に煎茶や食前酒が供され、その後先付けを勧める。この料理と器を取り巻く世界は複雑でありながらそうは見せさせないところに人の心を一旦引締め徐々に自然に解きほぐしていく秘密があるように考えられる。
茶道は茶と碗、華道は花と花器、能楽は謡と仕舞、料理は食材と器の関係がミニマムな世界であるが、料亭の懐石料理となると、料理を食することが主たる目的ではあるがこれら様々な伝統芸能からくる断片的な手法は同時且つ付随的に表現されることになる。料亭の明かりに導かれ長暖簾をくぐり、水を打った少し勾配のある露地を通る。日常から別離し非日常感を演出する。玄関には季節の軸が掛かり、その日のもてなしのテーマが映し出される。そしてその季節に関連した魚介類と野菜が調理され料理として供される。香が焚き染められ僅かに感じられるか感じられない程度の柔らかな香りに気分が落ち着く。料亭は個室なので、部屋ごとの設えはそのお客様の目的に応じて仕立てられている。お祝いの際には、能楽にもある「高砂」:世阿弥作(住吉明神の化身の老人夫婦)のお軸などをかけ、松をあしらった八寸を供し、長寿繁栄を願う気持ちを表現し、語ることなく相手に伝えるのである。基本的には「高砂」は春の演目であるので花入れには雪と春を印象付ける白梅を生けることになる。お席に着き、辺りを見回すとやや遠くに庭が見え、ガラス窓を挟んで縁側があり、その内に障子がはめ込まれ、上座には入り組んだ床の間があり、一番近いところに相伴する方々の顔がある。この凸凹した距離感の違いは狭い空間でも目が疲れず飽きない空間になっていて、されど強く目を引くものは全く存在しない。その状況下において食前に煎茶や食前酒が供され、その後先付けを勧める。この料理と器を取り巻く世界は複雑でありながらそうは見せさせないところに人の心を一旦引締め徐々に自然に解きほぐしていく秘密があるように考えられる。
懐石料理の献立は、先付・造り・煮物椀・八寸・焼物・焚合(蒸物)・酢物・御飯、香の物、止椀・水物という順に供されるのが一般的である。この懐石料理の構造は奈良時代以降、永続的に海外の食文化を国内で昇華しつつ、奈良時代の唐様、鎌倉時代の精進、平安時代の有職、室町時代の本膳、室町後期~江戸時代の茶懐石の要素を吸収しながら発展的に形成されてきた。現在でも数寄屋建築、能楽、茶道、華道といった文化が懐石料理と複合できるということは料理自体に人の情動に作用させ得る要素が非常に多く含まれているということが推察できる。やはり、懐石料理は意思(意識)を懐に入れ続けることによって、無限に拡張する料理なのである。
[掲載日:2018年11月1日]


