守旧派と改革派の役割
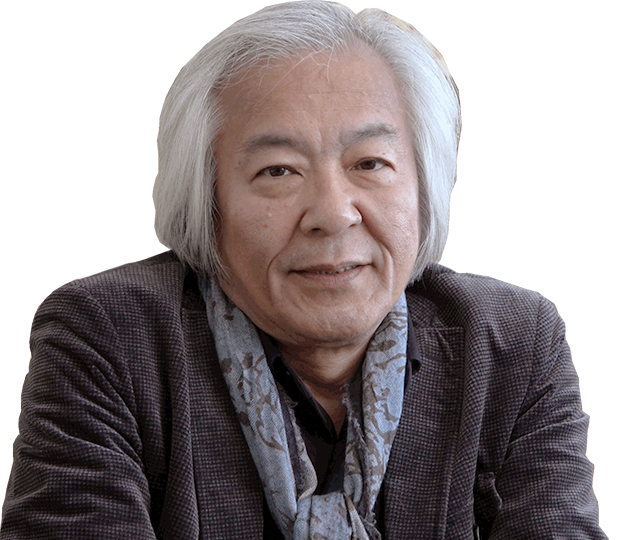
雑誌という視点から長いことプロの料理の世界を見てくると、関西というとどうしても日本料理にばかり注意が向きがちだが、考えてみれば、料理人を育てる調理師学校にしてもフランス料理の情報をいち早く世に出してきたのは「料理界の東大」あべの辻調理師専門学校だし、ここから多くの優れたフランス料理人を輩出していることも周知の事実だろう。
古いところでは神戸オリエンタルホテルの内海藤太郎などは、かの田中徳三郎(といっても知らない方が多いかもしれないが。パレスホテルの名料理長だった)が師と仰いでいた料理長で、帝国ホテルや旧大阪ホテルなどその足跡は東京から大阪、神戸と関西圏にも及んでいた。
そんな古い人たちをあげるとキリがないが、フランス料理というジャンルでは大阪にあったビストロ・ヴァンサンクの原彬容という人が私にとっては新しいフランス料理の流れを意識させられた存在だ。原からヌーヴェル・キュイジーヌという新しい潮流がフランスを大きく変えていることや、才能あふれる料理人、特にアラン・シャペルという存在を熱く語ってくれた。その話を聞いて、すぐにフランス取材を決意したのも、原からの影響が大きい。
以来30年以上、100店をはるかに超えるフランスの店を取材してきた。残念ながら原のいたヴァンサンクは店を閉め、彼はすでに現場にはいないようだが、いまでも料理の勉強会などには顔を出していると聞いているので、その勉強熱心な姿勢には頭が下がる思いだ。
 現代は、料理の世界も時代の流れは相当に早いが、そうした流れに掉さす古老がいつの時代にもいるものだ。あるときパリでジャン・ドラベーヌとシャルル・バリエというその時代の料理界のご意見番の二人が議論しているところに立ち会ったことがあるが、話の中心はヌーヴェル・キュイジーヌに対する罵倒で、なるほど業界というのはこうして守旧派と改革派が織り成しながら、前に少しずつ動いていくのだなと苦笑して聞いていたのを思い出す。
現代は、料理の世界も時代の流れは相当に早いが、そうした流れに掉さす古老がいつの時代にもいるものだ。あるときパリでジャン・ドラベーヌとシャルル・バリエというその時代の料理界のご意見番の二人が議論しているところに立ち会ったことがあるが、話の中心はヌーヴェル・キュイジーヌに対する罵倒で、なるほど業界というのはこうして守旧派と改革派が織り成しながら、前に少しずつ動いていくのだなと苦笑して聞いていたのを思い出す。
そんなとき、当の若い料理人はどんなことを考えていたのだろう。たとえばピエール・ガニェール。彼はいまや堂々たる三ツ星のシェフだが、彼がサン=テチエンヌでデビューしたころは、スニーカーを履いた若者で、同じ料理を決して作らないことで有名で、カルフォルニアのカフェのような店内を軽やかに皿をもってお客さんのもとに料理を運んでいた。
その時彼がこんなことを話してくれた。「ヌーヴェル・キュイジーヌが時代の潮流になった時に、いままで重苦しいと思っていた世界が、一気に青空が開けたように広がって本当にうれしかったものだ」と話していたのが印象的だった。若きガニェールにとっては、クラシックなフランス料理の世界はエスコフィエの呪縛でいっぱいで暗いものに映っていたのだろう。
そのヌーヴェル・キュイジーヌもだんだん勢いを失い、先日亡くなったジョエル・ロビュションがキュイジーヌ・モデルヌというネオ・クラシックな料理で登場して、時代がまた落ち着いた料理になっていく。
いまはフランスのガストロノミーを代表するミシュランより、アンチフランスのベスト50といったレストラン・ランキングが大流行で、その動きに一喜一憂する料理人の姿が目立つ。レストランがランキングという評価に馴染むものなのかは疑問がおおいが、外野席にいれば、面白くもエキサイティングにも写るのだろう。これもネット環境が整ったからだろうから、しばらくは続くのかもしれない。
北海道の美瑛というところで、オーベルジュと料理塾を運営するようになって、関西にはなかなか行けなくなったが、パワーの漲る関西のことだから、知らないうちにパワフルな料理人が台頭してきているのだろう。そんな彼らがどんな世界を創っていくのか、楽しみにしている。
[掲載日:2018年12月10日]


