その店に行くことの意味

大学を出て社会人になって以来、雑誌からWEBへと主戦場は変わったが、基本的にはメディアの仕事ばかりで20年以上を過ごしてきた。仕事を始めたころは、インターネットという世界が一般には開放されておらず、テレビをはじめとしたメディア4媒体が大きな力を持っていて、いま考えるといろんな意味でまだまだ大らかな時代だったなと思う。
そして20年ほど前にインターネットが私たちの生活に入り込んできてからは人々の生活スタイル、仕事のカタチ、そして僕たちメディアの存在意義は大きく変化した。
いまでは、メディアから流される情報は以前ほどの影響力を持たなくなり、口コミサイトやSNSで話題になることが店を経営する上で非常に重要なことになった。
そのため、検索にひっかかりやすいワードやSNSで話題になりやすい商売のスタイルやメニューの開発・PRに重きが置かれているような気がする。しかし、それはその店独自のスタイルではないことが多い。Aという店の劣化コピーのA’やBが街にあふれ、最初は話題になり、行列も生まれるが、そういった店に来る客はすぐに飽きるから、廃れるのも早い。
ここ数年、東京では高級寿司店が活況を呈している。銀座あたりでは会計がひとりあたり5万円オーバーとなる店も少なくなく、そういった店の予約が困難だったりする。もちろん味は美味しい。けれど、その5万円を支払うに値する店がどれほどあるのかということは別の話。話題だから一度は行こうかとなっても、二度目も訪れる店にはなかなか出逢えない。
魚の仕入れが高くなったとか銀座の一等地だからとか言うのは、店側の理屈であって、客にとってはそんな事情は知ったことではない。安くはない金額を支払うのだから、そこに見返りを求める。美味しさ、サービス、設え、、、そういったものは当たり前のこと。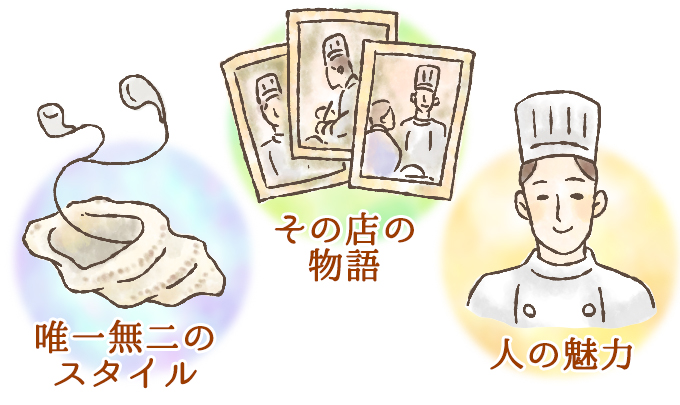 昨今の高級寿司店に出入りするのは銀座のクラブに行くことと同じように、ある種のコミュニティへの入会金を払っている気持ちかもしれない。会員制や紹介制のレストランにしてもそう。
昨今の高級寿司店に出入りするのは銀座のクラブに行くことと同じように、ある種のコミュニティへの入会金を払っている気持ちかもしれない。会員制や紹介制のレストランにしてもそう。
そこに求められているのは、その店の物語であったり、唯一無二のスタイルであったり、人の魅力であったり、さまざまだ。
そんなことを考えていると、時代は何も変わっていなかったことに気づく。
店の魅力はメディアのありよう、人々の行動様式が変わっても同じだ。
普通に美味しいものは簡単に手に入る時代だからこそ、飲食店にはその店でしか味わえない経験をさせてほしい。
店に行くことの意味は、そこにあるのだから。
[掲載日:2019年6月3日]


