料理人のための「新・こつの科学」Vol.4

現代の料理人に求められる「新・こつの科学」を考える。食べ手にどう感じさせたいかから発想し、そのためにはどのような成分をつくり出すべきか、そして調理技術はどうするか、という順序で料理を考える。今回は、『料理と飲み物の相性』について提案する。
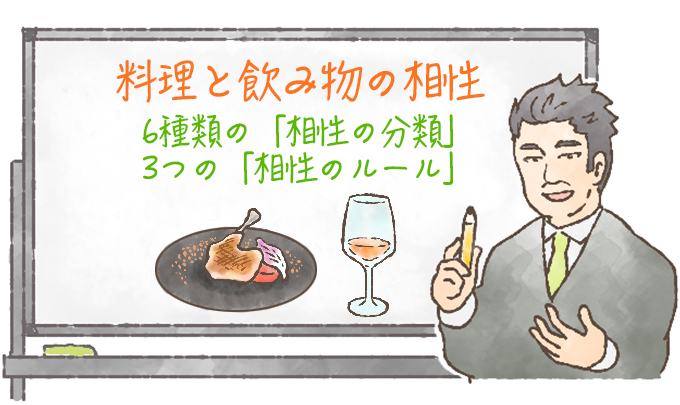 料理と飲み物の相性については、以前から『マリアージュ』や『ペアリング』という言い方で、論じられてきた。基本的には、料理と飲み物を一緒に味わったときに、おいしい、と感じている状態を指す。しかし、おいしい、とは個人差もあり、料理人の立場とソムリエの立場で異なることも多い。科学的な観点からすると、難しい問題でもまず分類することからすべてが始まる。そこで、プロとして相性を議論するために、自分の好みのおいしさに合うかどうか、ではなく、「どのようなおいしさ」なのかを議論できるように、「相性の分類」ができるのではないかと考えた。実際、これまでにもまとまった議論はないが、個別に相性の種類とでも言うべき科学的な研究報告も出てきているため、できるだけそのような知見も入れて、下記の6種類の「相性の分類」とその組み合わせとして3つの「相性のルール」を提案する。
料理と飲み物の相性については、以前から『マリアージュ』や『ペアリング』という言い方で、論じられてきた。基本的には、料理と飲み物を一緒に味わったときに、おいしい、と感じている状態を指す。しかし、おいしい、とは個人差もあり、料理人の立場とソムリエの立場で異なることも多い。科学的な観点からすると、難しい問題でもまず分類することからすべてが始まる。そこで、プロとして相性を議論するために、自分の好みのおいしさに合うかどうか、ではなく、「どのようなおいしさ」なのかを議論できるように、「相性の分類」ができるのではないかと考えた。実際、これまでにもまとまった議論はないが、個別に相性の種類とでも言うべき科学的な研究報告も出てきているため、できるだけそのような知見も入れて、下記の6種類の「相性の分類」とその組み合わせとして3つの「相性のルール」を提案する。
6つの相性の分類
1. 「WASH ウォッシュ」 飲み物が食べ物の油っこさのような嫌な印象を洗い流しておいしい、というような相性をWASHと分類した。アルコールには、油を溶かし込んで洗い流す作用があるため、そもそもお酒を食事のときに飲むと、油っこさを洗い流すことができる。また、赤ワインやお茶に含まれるタンニンは、唾液のたんぱく質と結びついて、油分を洗い流すことができる。さらに、近年、炭酸に、油脂を流す作用があることが報告されている。これらの作用を用いるのが、WASHという相性の分類で、例えば、唐揚げを食べた後に、炭酸の効いたビールを飲むと、「油が流されてさっぱりするのでおいしい」という状態になるので、「この相性の良さはWASHという言葉で表現しよう」と提案したのである。
2. 「NEWニュー」 飲み物と料理を同時に味わうことで、なにか新しい風味が感じられるときに、これはNEWの相性だと分類した。鼻にある匂いを感じる受容体の特性として、2種類の異なる香り成分を同時に感じると、単独では得られない風味が感じられることがある。法則性はなく、偶然発見されるようなものである。
3. 「SHAREシェア」 料理と飲み物で、香りや味わいが共通のものが含まれている場合に、SHAREという相性の分類とした。これまで、ソムリエや一般によく言われている相性の良さは、「このワインはベリー系のフルーツの香りがするので、料理にもベリーを使うと相性が良い」という表現ではないだろうか。あるベルギーのベンチャー企業は、その考え方を応用し、食材同士の相性の良さを教えるサービスを提供している。食材の香り成分の分析をして、食材ごとに共通の香り成分が含まれている場合は相性が良いとして、その食材を教えてくれるようなサービスである。ただ、共通の香り成分が含まれているからといって、おいしい、つまり相性が良いとは限らないので、あくまでヒントであり、実際には使う食材の量の調節も含めて作ってみて食べてみることが重要である。食材の組み合わせは、料理人の経験や発想がきっかけになるが、どうしても自分の枠を超えられないので、超えたい、という悩みがある場合には、有効なサービスかも知れない。
4. 「WEAK ウィーク/ STRONGストロング」 料理と飲み物が、互いに味わいや香りを弱めたり、強めたりしておいしく感じる場合の相性をWEAKまたはSTRONGとした。味覚という感覚の特性として、例えば酸味は、甘味を弱めて感じさせる。これを利用すると、酸味が強すぎるワインに、甘味のある料理を合わせると、ワインの酸味が和らいでおいしく感じるようになるかもしれない。
5. 「BAD FLAVORバッドフレーバー」 これは、相性が悪い場合の説明で、料理と飲み物を口に入れたときに、悪い匂いを感じるような場合を指す。これは鉄イオンを多く含むワインの場合、酸化しやすい魚介類の脂質を、口の中で酸化させる。酸化した脂質の匂いは、生臭さとして感じられ、極微量でも感じやすい。鉄イオンが含まれているかどうかは分析しないと分からないため、避けるためには、魚介類と合わせてみるしかないので、事前確認が重要である。
6. 「DOMINANTドミナント」 DOMINANTとは、支配的であるという意味だが、料理または飲み物のどちらかの味や香りの印象が強すぎる場合に、DOMINANTが偏っていて相性がよくない、という表現の分類とした。近年報告されている相性であり、DOMINANTが偏っていない料理と飲み物の組み合わせの場合に、おいしく感じる、という報告があるため、重要な相性の分類であると考えている。
3つの相性のルール
1. 「COMPLEXITY 複雑さ」 一般的には、料理や飲み物の風味は、単純なものより複雑であるほうがおいしいとされることが多いだろう。もしかすると単純というより単調と言い換えたほうが良いかもしれない。複数の味や風味を、料理と飲み物の組み合わせによって演出することで、贅沢な印象をもたらすような相性のことである。
2. 「HARMONY ハーモニー」 料理の飲み物をせっかく一緒に味わっているのに、単に様々な味や風味をバラバラに感じるのでは、おいしいとは感じないだろう。ハーモニーや調和というのは、具体的に説明することは難しく、好みもある。例えば、料理だけとっても、インド料理では、複数のスパイスをきちんと個別に感じ分けられるような使い方が好まれるが、日本人が好むカレーは、「二日目のカレーがおいしい」と言われるように、それぞれのスパイスの個性というより、全体としてのスパイスの調和が重視される。料理と飲み物の相性についてもHARMONYが良いという感覚はどのようなものか、今後の研究が期待される。
3. 「BALANCEバランス」 料理と飲み物の強さの印象が同じような組み合わせの場合をBALANCEの良い相性とした。DOMINANTの項で述べたように、DOMINANTが料理と飲み物で偏っていない、つまりどちらかが強かったりしない組み合わせの場合に、おいしく感じる、という報告があるためである。
これらの6つの相性の分類を、3つのルールを意識しながら使い分け、相性を議論すれば、単に「これがおいしい」ということではなく、ある程度客観的に議論ができるのではないか。さらには他にも相性の分類やルールがあるかもしれない。ぜひ新たな分類やルールを発見したら、提案して共有し、皆で議論していくことで、研究が深まっていくと思われる。
[掲載日:2021年10月1日]


